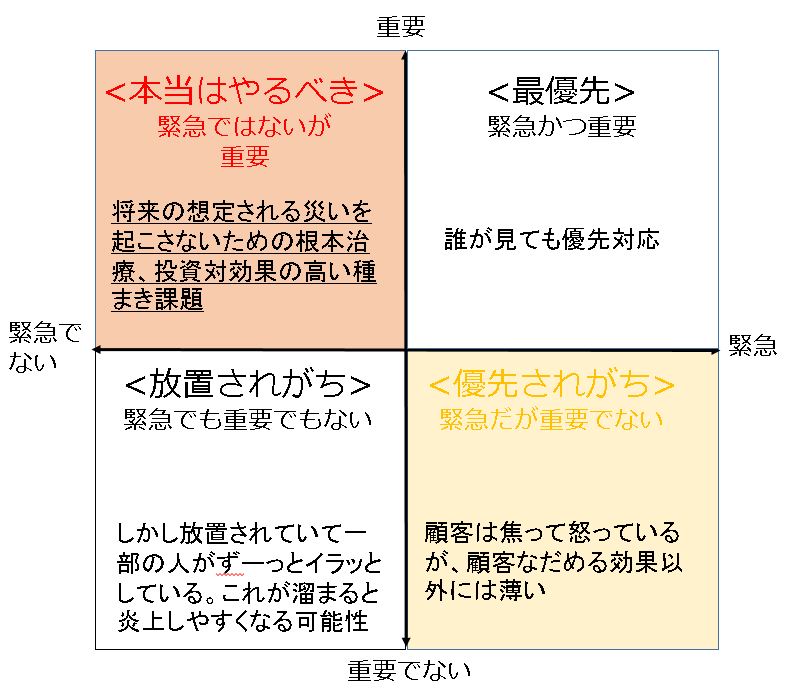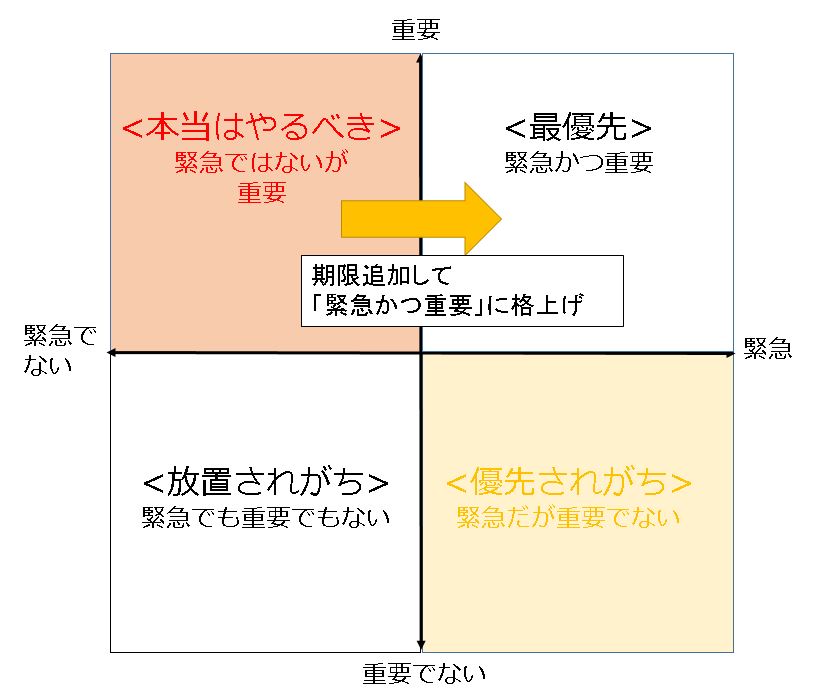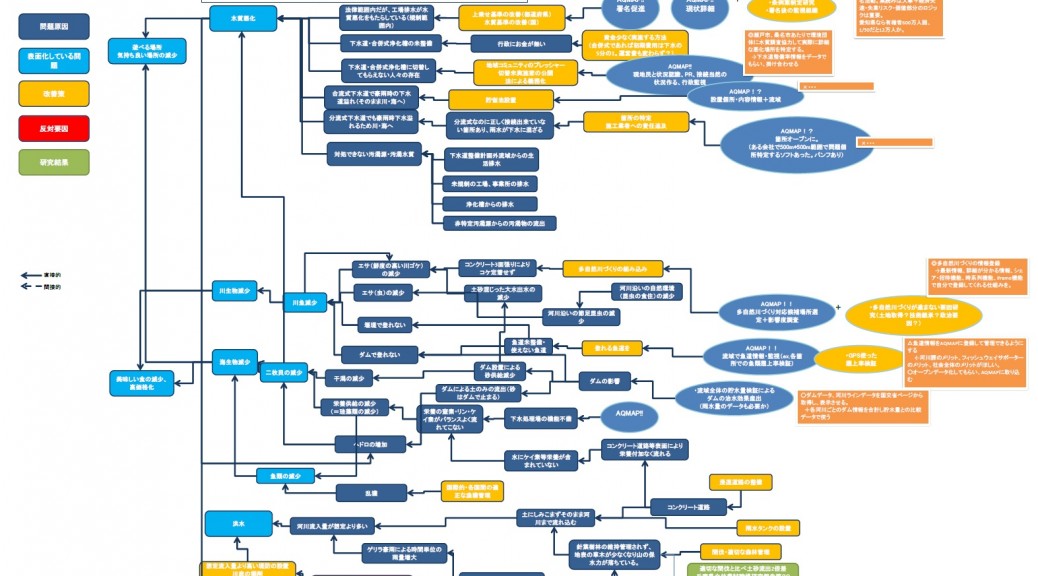「プライドを持て!」「プライドは無いのか」そんな言葉があり、プライドは仕事の成果を高める上で一つの重要な意識と考えられる。
一方で、「あの人プライド高いよね」という言葉はマイナスの意味(人の言うこと聞かない、独りよがり)で言われる。
成果を出す上で「プライドを捨てろ」という話も言われる。
同じプライドなのに?
プライドには2種類あると気づいた。
外向けのプライドと、内向けのプライド。
成果・作品に対するプライドと、自分をよく見せるためのプライド。
仕事において良い効果を与えるプライドは前者。後者は悪い効果を与える。
ちなみに、プライドの意味は「誇り」「自尊心」。prideの語源はフランス語で、「誇り」の意味で使っていたが、イギリス人から見るとそれが「思い上がり」や「高慢」に見えたとのことで、それらの意味も含んでいる。
自分に向いたプライドは、それだけの自信・自負があるのかもしれないが、それは一方で「資産」であり、無くしてはいけないものになってしまう。
カッコよさにプライドを持ってしまうと、カッコ悪いことが出来なくなる。
すごい人であるというプライドを自身に持ってしまうと、失敗が怖くなる。人より自分が優れていると思うため、人の話・アドバイスを聞けなくなる。出来ない人の典型パターンになる。
(年老いて人の話を聞けなくなるのも、このプライドとの関係かな。能力は下がってくるが出来てきた自分の「資産」は増えていくため、より困った人になりがちになるのかも。他山の石として人生で気をつけるべきことかな。)
一方で、外向けのプライド。
自分が作った製品・作品へのプライド。これは持っていないと、喜ばれる、品質の高い、感銘を受けるような創造物は作れない。
自分が作ったプログラムへのプライドが無ければ、人にどう使われても、どのように言われても気にならないので、品質を高くしようという努力もされないし、素晴らしく使い勝手の良いソフトに作り込む意欲も湧いてこないだろう。
自分へのつまらないプライドは捨て、自分が作り出すものへのプライドを持つ。
人はその人が出す成果を通してその人の人間性を、その人のすごさを見ている。
プライドの持ち方も、そのラインを勘違いするとタダのイタい人になる。